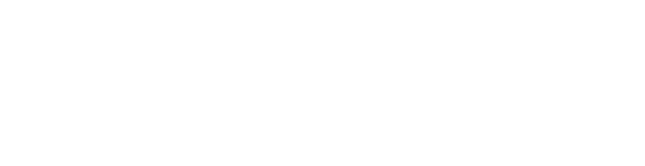社会・経済の動き@しんぶん
社会・経済の動き@しんぶん
 社会・経済の動き記事一覧
社会・経済の動き記事一覧
-
日銀は7月28日の金融政策決定会合で、長期金利の上限について0.5%程度をめどとし、市場の動向次第では1%まで上昇することを容認することを決定した。植田日銀総裁は会見で「1%まで上昇することは想定していないが、念のための上限として1%とした」と述べた。これに先立つ7月2 ……(続きを見る)
-
総務省が発表した6月の全国消費者物価指数(2022年=100)は前年同月比3.3%上昇の105.0だったことが分かった。22ヵ月連続で前年同月を上回っている。背景には食料や日用品の値上げに加えて、6月の大手電力が実施した規制料金の引き上げが挙げられている。一方、内閣府が ……(続きを見る)
-
欧州連合(EU)は2011年の東京電力福島第一原発事故後に福島県など10県の一部食品を対象に義務付けてきた放射能物質の検査証明書を不要とするなど、日本産食品に課してきた輸入規制を撤廃すると発表した。EU内での手続きを経て、早ければ8月上旬にも撤廃される見通しとなった。輸 ……(続きを見る)
-
国際原子力機関(IAEA)は東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出に関して、「放出計画は国際的な安全基準に合致する」との包括報告書を発表した。この報告書を経て、政府が「夏ごろ」としていた放出開始の具体的な時期の検討に入ることになる。また、処理水の海洋放出計画を巡り、原子 ……(続きを見る)
-
帝国データバンクの予想によると、2023年の食品の値上げは3万5千品目に達し、2022年通年での値上げされた2万5768品目を大きく上回る見通しにあることが明らかになった。原材料高と円安の進行により輸入物価が押し上げられたことに加え、その分の価格転嫁が進むとみている。同 ……(続きを見る)
-
2022年度の国の一般会計の税収が過去最高を3年連続で更新する見通しにある。年度税収は3月期決算法人の法人税や消費税など確定する5月分を加えた上で確定するが、4月末時点で既に61兆5325億円となっており、過去5年間を見ると5月分は8~10兆円増えており、年度税収は70 ……(続きを見る)
-
6月15日、東京外国為替市場での円相場は1ドル=141円50銭を付け、昨年11月以来、約7か月ぶりの円安ドル高水準となった。米連邦準備制度理事会(FRB)が利上げを年内にあと2回の実施継続する可能性を示したのに対し、日銀は大規模な金融緩和策を継続するとしており、その方向 ……(続きを見る)
-
厚生労働省の速報によると、1人の女性が生涯で出産する子ども数を示す合計特殊出生率は昨年1年間で1.26となり、過去最低となったことが明らかになった。合計特殊出生率は前年比0.05ポイント下がり、7年連続での減少となっている。一方、昨年1年間に死亡した人は156万8961 ……(続きを見る)
-
政府は5月の月例経済報告で、国内景気の基調判断を「緩やかに回復している」に引き上げた。上方修正は10カ月ぶりで、新型コロナウイルス感染が拡大して以降で初めて「回復」との表現を用いた。現状判断の個別項目では、個人消費を「緩やかに持ち直している」から「持ち直している」と上方 ……(続きを見る)
-
内閣府は2023年1~3月期の国内総生産(GDP)は物価変動を除く実質で前期比0.4%増となり、年率換算で1.6%増となったと発表した。3四半期ぶりのプラス成長となった背景には新型コロナウイルス感染が落ち着きを見せ、旅行などの個人消費が回復したことに加え、設備投資の増加 ……(続きを見る)
-
世界保健機関(WHO)は5月5日、2020年1月に宣言した新型コロナウイルス緊急事態の終了を発表した。専門家会合で新型コロナウイルスの流行がもはや緊急事態に当たらないという見解を受け、宣言の解除を行ったもので、宣言から3年3カ月余を経て、「平時」への移行へと踏み出したこ ……(続きを見る)
-
財務省の発表によると、国債と借入金、政府短期証券を合わせた、いわゆる国の借金は2022年度末時点で1270兆4990億円になったことが明らかになった。2022年度は約29兆円増え、過去最大を更新した。背景には、新型コロナウイルスや物価高対策による財政出動が図られたことが ……(続きを見る)
-
財務省は2022年度貿易統計速報で貿易収支は21兆7285億円の赤字だったと発表した。赤字額は前年度比約3.9倍もの急増ぶりで、比較可能な1979年度以降で過去最大となった。背景には原油価格の高騰や円安があり、輸入が前年度比32.2%増の120兆9550億円となり、輸出 ……(続きを見る)
-
総務省は2022年10月1日時点での人口推計で、外国人を含む総人口は1億2494万7千人となり、12年連続でマイナスを記録したと発表した。日本人だけでみると、過去最大となる75万人が減少し、1億2203万1千人となった。総人口の年齢別は15~64歳の生産年齢人口は29万 ……(続きを見る)
-
国際通貨基金(IMF)は4月11日に世界経済見通しを発表するが、これに先立ってゲオルギエバ専務理事は「2023年は先進国の9割で成長率が低下すると予測している」との見解を講演で示した。同氏は「2023年世界経済の成長率は3%未満になり、今後5年間は3%前後で推移する」と ……(続きを見る)
-
3月28日、参議院本会議で2023年度予算が成立した。過去最大規模の114兆円台となり、一般歳出で防衛費が26.3%もの大幅な増加で、社会保障費に次いで2番目の歳出規模となり、公共事業費や文教科学振興費を上回る突出している。また、2023年度予算では新規の国債発行額は3 ……(続きを見る)
-
国土交通省の公示地価(2023年1月1日時点)は全用途の全国平均が前年比1.6%上昇していたことが明らかになった。2年連続での上昇で、住宅地、商業地のいずれも上昇した。住宅地は東京、名古屋、大阪の3大都市圏は昨年の0.5%から1.7%と上昇率が高く、地方4市の札幌、仙台 ……(続きを見る)
-
財務省が発表した今年2月の経常収支は8977億円の赤字となったことが明らかになった。2月単月でみると、1979年以降では過去最大となった。2月の輸入は前年同月比8.3%増の8兆5524億円、輸出は6.5%増の7兆6547億円で、輸出入いずれも2月単月としては過去最大だっ ……(続きを見る)
-
財務省が発表した今年1月の経常収支は1兆9766億円の赤字となり、1985年以降で過去最大の赤字となったことが明らかになった。前年同月比で1兆3962億円もの赤字幅が増大した背景には、輸入額は前年同月比17.8%増と大幅な増加となり、円安やエネルギー価格の高騰で10兆4 ……(続きを見る)
-
厚生労働省の人口動態統計によると、2022年の出生数は79万9728人となり、統計開始以来、初めて80万人を割り込んだ。国の推計では80万人を割り込むのは2033年と見込んでいたが、推計を10年以上早いペースで少子化が進んでいる実態にある。7年連続で出生数は過去最少を更 ……(続きを見る)
-
財務省は2022年度の国民負担率は47.5%になるとの見込みを発表した。国民負担率は国民や企業が所得の中から税金や社会保険料を支払っているかを示すもので、過去最大だった前年度を0.6ポイント下回った。内訳をみると、税負担が28.6%、社会保障負担が18.8%だった。国民 ……(続きを見る)
-
財務省は1月の貿易統計で貿易収支は3兆4966億円の赤字だったと発表した。貿易赤字は比較可能な1979年以降、単月としては過去最大となるとともに、3兆円を超えたのは初めてとなる。貿易赤字は18か月連続となる。原油などの資源エネルギー高に加え、為替レートが平均で前年同月か ……(続きを見る)
-
政府の発表によると、2022年末時点での国債と借入金、政府短期証券を合計した、いわゆる「国の借金」は過去最大を更新する1256兆9992億円に上ることが明らかになった。このうち普通国債残高は1005兆7772億円に上り、初めて1千兆円を突破した。昨年9月末時点での「国の ……(続きを見る)
-
世界保健機構(WHO)は専門家による緊急委員会を開き、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の是非や解除条件を協議した結果、2020年1月に宣言した「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を継続する方針を発表した。委員会では新型コロナウイルスが依然危険な感染症であると ……(続きを見る)
-
政府は1月27日、新型コロナウイルスの感染症上の位置づけを現在の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げることを正式に決定した。これにより、感染対策のための外出自粛要請や大規模イベントの人数制限がなくなることになるが、政府は3月上旬をめどに引き下げ以 ……(続きを見る)
-
財務省が公表した2022年の貿易統計での貿易赤字額は19兆9713億円に上り、1979年以降で過去最大となることが明らかになった。赤字額は2021年よりも18兆円余り増えており、背景にはロシアのウクライナ侵攻などでエネルギー価格の高騰したことや円安などにより輸入額が輸出 ……(続きを見る)
-
世界銀行は世界経済見通しで2023年の全体の実質成長率を1.7%と予測した。2022年6月時点の前回予測から1.3ポイント下落の大幅な下方修正となった。予測の背景には、先進国の中央銀行による利上げやロシアのウクライナ侵攻が長引いていることが挙げられている。世銀は「コロナ ……(続きを見る)
-
財務省は1月5日実施した1月発行の10年物国債の入札で、買い手に支払う利子の割合である「表面利率」を前月までの年0.2%から0.5%に引き上げた。背景には日銀の金融緩和を修正して実質利上げに踏み切ったことから市場では長期金利が上昇してきており、買い手に国債を引き受けてく ……(続きを見る)
-
12月23日、政府は2023年度一般会計の歳出総額が過去最大となる114兆3812億円となる予算案を閣議決定した。予算案では防衛力強化を最重要課題として防衛関連では米軍再編経費を含め過去最大となる6兆8219億円を確保し、前年度比1.26倍に増やした。歳出で最も多くを占 ……(続きを見る)
-
国際通貨基金(IMF)の発表によると、2021年の世界の公的債務と民間債務の合計が国内総生産(GDP)の247%に上ることが明らかになった。新型コロナウイルス禍対策で各国政府が財政出動したことで、コロナ禍前の2019年(228%)時より増えているものの、2020年時点で ……(続きを見る)