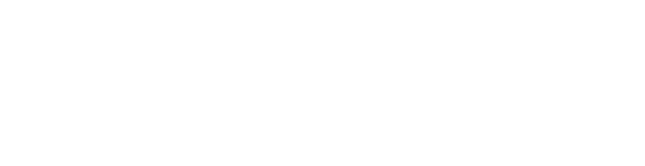社会・経済の動き@しんぶん
社会・経済の動き@しんぶん
 社会・経済の動き記事一覧
社会・経済の動き記事一覧
-
国際通貨基金(IMF)のゲオルギエワ専務理事はIMF・世界銀行年次総会で「世界経済が低成長・高債務に陥る恐れがあり、各国政府は国民の機会や意欲を向上させることや、気候変動などの課題に取り組む財源を失うことになる」としたうえで、「国民の不満は一層高まる」と警鐘を発した。ま ……(続きを見る)
-
観光庁は1~9月に日本を訪れた外国人の宿泊や買い物などによる消費額は5兆8582億円だったと発表した。これまで年間最高を記録した2023年の5兆3065億円を9月末で超え、今年度は最高を更新することが明らかになった。円安が追い風となり、訪日外国人が増加するとともに、宿泊 ……(続きを見る)
-
2024年ノーベル平和賞に日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)が選ばれた。ノーベル平和賞に選出されたことについて日本被団協の箕牧代表委員は「戦後79年の成果。世界に1つしかない成果ですから、それが日本被団協なるなんて夢にも思わなかった」との感慨を会見で述べた。また、 ……(続きを見る)
-
帝国データバンクの調査によると、10月に値上げが予定されている食品は2911品目に及び、品目数としては4月の2897品目を上回り、今年最多となることが明らかになった。値上げの背景には、原材料高、物流費や人件費の上昇が挙げられている。同社では「円安による値上げが一服するも ……(続きを見る)
-
石油輸出国機構(OPEC)が発表した「2024年版世界石油見通し」で、2050年の世界の石油需要は2023年比で18%増の日量1億2010万バーレルに上ると予測していることが分かった。その上で、OPECは石油需要増加に応えるうえで、2050年までに17兆4千億ドル(25 ……(続きを見る)
-
国土交通省が発表した7月1日時点での都道府県地価(基準地価)は住宅地と商業地、全用途の全国平均が3年連続で上昇した。全国平均の上昇率は、住宅地が前年比0.2ポイント増の0.9%、商業地は同0.9ポイント増の2.4%となり、上昇率はいずれもバブル経済崩壊で大きく下落した1 ……(続きを見る)
-
9月13日の東京外国為替市場の円相場が対ドルで1%を超える上昇で、一時1ドル=140円65銭となった。2023年12月下旬以来の約8か月半ぶりの円高ドル安水準となった。米国の景気悪化懸念が再燃したことに加え、米連邦準備制度理事会(FRB)が来週の会合で大幅な利下げ観測、 ……(続きを見る)
-
厚生労働省が発表した7月の毎月勤労統計調査で、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月比0.4%増となり、2ヵ月連続でプラスとなったことが明らかになった。6、7月ともに夏の賞与の伸びが底上げしたことが実質賃金の伸びにつながっており、今後も物価上昇率を上回るかどう ……(続きを見る)
-
厚生労働省が2024年度都道府県別の最低賃金を集計したところ、時給の全国平均は前年度比51円増の1055円だったことが明らかになった。前年度からの引き上げ額は過去最大で、国が示した「目安額」の50円を27県で上回った。物価高や人手不足、歴史的な賃上げとなった今春闘を背景 ……(続きを見る)
-
政府が閣議決定した経済財政運営指針「骨太方針」と成長戦略「新しい資本主義実行計画」で、基礎的財政収支(プライマリーバランス)を2025年度に黒字化する目標を堅持したものの、2026年度以降の具体的な黒字化目標は見送った。骨太方針では2030年度までの財政健全化計画を提示 ……(続きを見る)
-
内閣府は2024年4~6月期の名目国内総生産(GDP)は年率換算で物価上昇を背景に約607兆円となり、初めて600兆円を超えたと発表した。物価変動の影響を除いた実質GDPの実額は約559兆円で、前年同期の約563兆円を下回っている。GDPの約6割を占める個人消費だが、物 ……(続きを見る)
-
総務省は人口動態調査で今年1月1日時点での外国人を含む総人口は1億2488万5175人だったと発表した。前年比約53万人下回っており、日本人に限定すると1億2156万1801人となり、約86万1千人減少している。15年連続での減少。死者数が過去最多の約158万人で、出生 ……(続きを見る)
-
国際通貨基金(IMF)は世界経済見通しで、今年の世界全体の実質成長率を3.2%とした。日本は4月時点の予測から0.2ポイント下方修正の0.7%とした。IMFは「米国と中国などの貿易摩擦の激化が経済に与える悪影響を及ぼす」との懸念を示すとともに、「今年の選挙結果で経済政策 ……(続きを見る)
-
国連は世界の人口が2080年代半ばにピークに到達するとの見通しを発表した。国連の報告書によれば、現在82億人の世界人口は、2080年代半ばに103億人のピークに達すると予想し、その後は緩やかに減少を辿り、今世紀末には102億人になるとしている。今年73.3歳に達した平均 ……(続きを見る)
-
7月1日のニューヨーク外国為替市場で、一時、1ドル=161円70銭台となり、円安ドル高となった。米国では1日朝に長期金利の上昇とともに、円が売られドルが買われた。背景には米連邦準備制度理事会(FRB)での利下げが遠のき、ドルと円の金利差が縮まらないとの観測から、高金利で ……(続きを見る)
-
6月26日に外国為替市場で、一時、1ドル=160円60銭台となり、バブル経済期が始まった1986年12月以来約38年ぶりの円安ドル高の水準となった。背景には米連邦準備制度理事会(FRB)での早期に利下げするとの観測が後退し、高金利で運用に有利なドルを買って円を売る動きが ……(続きを見る)
-
国際決済銀行(BIS)は日本「円」の国際的価値を示す実質実効為替レート(2020年=100)が5月は68.65となったと発表した。過去最低を更新するもので、ピーク時の1995年4月(193.97)の約3分の1にまで落ち込んだ。背景には、海外と比べ物価や賃金の伸びが鈍いこ ……(続きを見る)
-
厚生労働省は2023年の人口動態統計で、女性が生涯に産む子どもの推定人数である合計特殊出生率は過去最低の1.20となったと発表した。8年連続でマイナスとなり、出生数は過去最少の72万7277人だった。2024年の出生数は70万人を下回る可能性がある。都道府県別の出生率に ……(続きを見る)
-
財務省の発表によると、政府・日銀が4月から5月にかけて実施した外国為替介入額総額は9兆7885億円だったことが明らかになった。4月26日~5月29日までの1ヵ月で、円買い・ドル売りの為替介入として、2022年10月の6兆3499億円を上回るもので、過去最大となった。為替 ……(続きを見る)
-
5月22日の国債市場で長期金利は1.0%を付けた。2013年5月以来、11年ぶりの高水準。長期金利が上昇した背景には、日銀が国債購入額を本格的に減らし、金融政策の正常化を早めるとの見方が高まったことが挙げられている。為替相場で一段の円安進行ともなれば、日銀はさらなる正常 ……(続きを見る)
-
内閣府は2024年1~3月期の国内総生産(GDP)は物価変動を除く実質で前期比0.5%減の年率換算2.0%減だったと発表した。2四半期ぶりのマイナス成長の背景には、個人消費が4期連続での減少が響いた。設備投資は新車購入の減少が影響して0.8%減、輸出はインバウンド消費が ……(続きを見る)
-
財務省は2023年度末(3月末時点)での国債や借入金などを合わせた、いわゆる「国の借金」は1297兆1615億円となったと発表した。前年同月比26兆6625億円増となり、8年連続で過去最大を更新した。防衛費や社会保障費が増えたことに加え、ガソリン補助金や低所得者世帯への ……(続きを見る)
-
国際通貨基金(IMF)の推計によると、2025年時点での日本の名目GDP(国内総生産)は4兆3103億ドルで、世界5位のインドは4兆3398億ドルに上昇し、日本は世界5位に転落する見通しとなることが発表された。日本の名目GDPは2023年通年のGDP速報値でドイツに抜か ……(続きを見る)
-
4月27日の東京外国為替市場の円相場は158円40銭台となり、約34年ぶりの円安ドル高となった。米長期金利が上昇したことで、今後日米の金利差拡大から円が売られドル買いが進んだ。同日行われた日銀の金融政策決定会合で現行の政策金利を維持するとの決定がされ、今後、日米の金利差 ……(続きを見る)
-
国際通貨基金(IMF)が公表した2024年の世界全体の実質成長率は3.2%とする見通しであることが分かった。今年1月時点から0.1ポイント上方修正した背景には、米国の底堅い経済動向やインドなどの新興国の成長を挙げた。IMFでは「世界経済は依然として堅調」と指摘しながらも ……(続きを見る)
-
総務省は2023年10月末時点での人口推計で外国人を含む総人口は1億2435万2千人だったと発表した。13年連続のマイナスで、日本人は83万7千人減の1億2119万3千人だった。年齢別にみると、後期高齢者となる75歳以上は71万3千人増の2007万8千人となり、初めて2 ……(続きを見る)
-
連合が発表した2024年春闘の中間回答集計によると、基本給を底上げするベースアップと定期昇給を合わせた賃上げ率(加重平均)は5.24%となることが分かった。組合員数1000人以上の大手の賃上げ率は5.28%で、組合員数が300人未満の中小は4.69%だった。連合では「中 ……(続きを見る)
-
3月28日、参議院本会議で一般会計総額112兆円の2024年度予算が可決・成立した。歳出総額が112兆5717億円となり、2年連続で110兆円を超え、過去2番目の規模となる。全体の3分の1を占める医療や年金に当てられる社会保障関係費は37兆7193億円、防衛費は5年以内 ……(続きを見る)
-
3月19日の日銀金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の柱となるマイナス金利政策の解除を決定した。長期金利を低く抑える長短金利操作も撤廃し、3月21日から政策金利を0~0.1%とするとともに、上場投資信託(ETF)の新規買い入れも終了する一方、金利の急上昇を防ぐために長期 ……(続きを見る)
-
2024年3月16日、北陸新幹線の金沢-敦賀間が延伸開業した。1973年に整備計画が決定されてから51年目となり、新幹線網が福井県に広がったことになる。これにより、東京-福井間の所要時間は最短で2時間51分となり、これまでの東海道新幹線と在来線特急を乗り継ぐことにより3 ……(続きを見る)