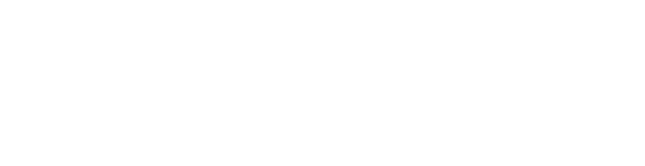どっと読む5/6号(第1129号)
どっと読む5/6号(第1129号)
IMF、世界経済成長率を2.8%に引下げ
国際通貨基金(IMF)は2025年の世界全体の実質成長率を2.8%に引き下げる見通しを発表した。1月時点から0.5ポイント引き下げたことになるが、背景にトランプ米政権の関税強化や貿易摩擦の激化などの影響が挙げられている。日本も0.5ポイント引き下げて0.6%とするなど、大半の国の実質成長率を引き下げている。IMFでは「世界的な景気後退は予測していないが、リスクは高まっている」と指摘している。
日銀、成長率予測を大幅に引き下げ
5月1日に開かれた日銀の金融政策決定会合で、2025年度の実質国内総生産(GDP)成長率を1月時点での予測(1.1%)を0.5%にした。大幅に引き下げた背景には、トランプ米政権の関税強化政策により貿易摩擦が激化し、世界経済が急激に減速し、国内企業の収益が大幅に減少すると判断したことが挙げられている。このため、政策金利を0.5%程度で据え置くことを決定した。また、日銀は物価上昇率を2%程度で安定させる目標を1年程度遅れるとの見通しも示した。
米GDP、1-3月期は3年ぶりのマイナス
米商務省は1~3月期の実質国内総生産(GDP)は年率換算で前期比0.3%減だったと発表した。2022年1~3月期以来、3年ぶりのマイナス成長となった。前期(2024年10~12月期)は2.4%増から一転してマイナス成長に転じた背景には、トランプ米政権の関税措置の本格導入を前に、GDPがマイナスに作用する「輸入」が駆け込みで急増したことが挙げられている。GDP発表後のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は前日から一時700ドルも値を下げた。
15歳未満の子ども、44年連続で減少
総務省が発表した15歳未満の子どもの数(4月1日自伝での推計)は1366万人だったと発表した。減少は44年連続となり、1400万人を初めて割り込んだ。内訳は、男性が699万人、女性が666万人だった。減少が開始する前の1981年の子どもの数は2760万人だったが、現在はその半分以下となる。また、総人口に占める子どもの割合は11.1%となる。子どもの数は47都道府県全てで減少し、100万人を超えたのは東京都と神奈川県だけで、最少は鳥取県の6万3000人だった。
2024年世界軍事費、過去最高を更新
ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は2024年の世界の軍事費が前年比9.4%増の2兆7180億ドル(約390兆円)になったと発表した。過去最高を更新したもので、増加は10年連続となる。背景に、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や中東での紛争拡大など世界的な緊張激化が挙げられている。国別にみると、米国が1位(9970億ドル)で、2位の中国と合わせて全体のほぼ半分となっている。
コメ平均価格、16週連続で最高値を更新
農林水産省の発表によると、4月14~20日に全国のスーパーで販売されたコメ5キロ当たりの平均価格は4220円だったことが明らかになった。16週連続で最高値を更新してきており、前年同期の2088円と比べて約2倍となっている。一方、政府の備蓄米流通は落札された2回分の放出量は1.97%にとどまっており、消費の現場に届いていない実態も明らかになっている。政府は7月頃まで毎月備蓄米を放出する方針を掲げている。
健保連、平均保険料率が最高の9.34%
大企業の社員らが加盟する全国の健保組合の2025年度予算推計によると、平均保険料率は前年度比0.03ポイント増の過去最高となる9.34%だったことが明らかになった。経常収支は3782億円の赤字を見込んでおり、背景には高齢者医療を支えるために現役世代が拠出する「支援金」が膨らんだことが挙げられている。とくに、2025年に団塊世代が全員75歳以上の後期高齢者入りすることが響いており、賃上げや女性の就労促進などで保険料収入は伸びるものの、赤字解消には至っていない。
関西万博の来場者、50歳以上が7割強
スマートフォンの位置情報を分析するクロスロケーションズの調査によると、大阪・関西万博の来場者を開幕日の4月13日~24日までに会場内に滞在した人のデータから性別・年代別の割合を推計したところ、7割強が50歳以上と推計されることが分かった。逆に、20代が5%、30代が6%で、若い世代の来場者は少なかった。男女別では、男性が45%、女性が55%だった。開幕から半年で万博協会が想定する2820万人を達成するためには1日平均15万人の来場者が必要だが、調査期間中は1度も届いていない。