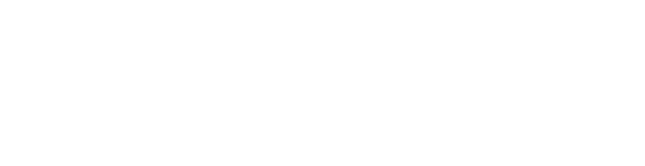どっと読む4/15号(第1127号)
どっと読む4/15号(第1127号)
米景気、後退確率を45%に引き上げ
ゴールドマン・サックスは米国の景気後退確率(リセッション)が今後12ヵ月以内に起きる確率は従来の35%から45%に引き上げた。後退確率を引き上げた背景には、広範な関税導入により貿易戦争への懸念が広がっていることが挙げられた。同社は1週間前に、米国のリセッション確率を20%から35%に引き上げたばかりで、米国の景気後退が一段と進むとみている。また、JPモルガンは米国および世界経済がリセッションに陥る確率は60%としている。
東証、4月第一週の下げ幅は過去最大
4月4日の東京株式市場での終値は3万3780円58銭となり、昨年8月以来約8か月ぶりの安値水準で終えた。4月第一週間の終値下げ幅は3339円に達し、週間下げ幅は過去最大となった。東京株式市場では、貿易摩擦の警戒感から輸出関連株に売り注文が殺到した。株式市場から投資資金を引き揚げる動きが優勢となった。一方、外国為替市場は円買いドル売りが優勢となり、一時、1ドル=144円台まで円高が進んだ。
2月の実質賃金、2カ月連続で減少
厚生労働省が公表した毎月勤労統計調査で物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月比1.2%減だったことが分かった。2カ月連続でのマイナスで、物価高騰に賃上げが追いついていない状況を示している。2月の名目賃金にあたる現金給与総額は3.1%増の28万9562円で38ヵ月連続プラスとなっている。しかし、消費者物価指数が4.3%上昇しており、実質賃金はマイナスとなっている。実質賃金は2024年5月まで過去最長となる26ヵ月連続でマイナスを記録し、その後は夏・冬のボーナスが支給された月だけがプラスとなっている。
後継者難倒産、2年連続で500件超に
帝国データバンクの調べによると、2024年度に後継者がいないことで事業継続が困難になった「後継者難倒産」は507件となり、2年連続で500件を上回ったことが明らかになった。過去2番目の高水準にあり、業種別にみると、建設業が127件と全体の25%を占め、次いで、製造業(88件)、サービス業(87件)が続いた。後継者難倒産が続く背景には、社長の高齢化が挙げられており、2024年の後継者難倒産の倒産時の社長の平均年齢は69.8歳となっている。
2024年度、企業物価指数は3.3%上昇
日銀は2024年度平均の国内企業物価指数(2020年平均=100)は前年度比3.3%上昇の123.9だったと発表した。前年度の伸び率2.4%から拡大しており、指数水準は比較可能な1980年度以降で最高だった。背景には、政府による電気・ガス代の補助縮小に加えて、コメ価格の高騰、さらに円安による輸入物価の高止まりから企業の負担増となっている。こうした負担増の価格転嫁が企業の今後の盛衰を分ける一因ともなっている。
内閣府初集計、「孤立死」は年2.2万人
内閣府が初めて推計調査した2024年の「孤立死」は2万1856人だったことが明らかになった。「孤立死」は自宅で1人暮らしの人で、誰にも看取られなく亡くなり、死後8日以上経過して発見された人を指し、生前、社会的に孤立していたとみられる死亡したものと定義されている。内閣府は「単身世帯の増加により孤独や孤立の問題が深刻化する懸念がある」と指摘している。今後、内閣府では自治体と連携し、孤立死を防ぐ対策を検討する方針を示している。
2021年、全国のがん患者は98万人
厚生労働省が全ての患者数を集計する「全国がん登録」のデータを分析したところ、2021年にがんと診断された患者は98万8900人だったと発表した。前年から約4万4千人増えている。男性が55万518人、女性が43万2982人。男性の部位別では最も多かったのは前立腺がんが9万5584人で50代後半から急増し、女性は乳がんが9万8782人で30代前半から増えている。人口10万人当たりの患者数で多かったのは秋田(424人)で、最も少ないのは宮崎(344人)だった。
大学生バイト就労率、最高の76.8%
全国大学生活協同組合連合会が全国の国公立大と私立大の学部生約5万人を対象にとしたアンケート調査によると、学生全体のアルバイト就労率が過去10年で最高の76.8%に上ることが分かった。日常悩むことを尋ねたところ(複数回答)、「生活費やお金」(44.7%)が最多で、「勉学のこと」(44.7%)、「就職」(37.8%)が続いた。自由記述では「物価高で生活が苦しい」「買いたいものを諦めることが増えた」の回答が目立ち、中には「奨学金の返済が怖く、漠然とした不安がある」との回答もあった。